
新入荷
再入荷
数々の賞を受賞 楽天市場】【茶道具/茶器 建水】 唐銅(唐金) 伝来形 不審庵 その他
 タイムセール
タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(※)
999円以上お買上げで代引き手数料無料
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
商品詳細情報
| 管理番号 |
新品 :16128616962
中古 :16128616962-1 |
メーカー | 621602937 | 発売日 | 2025-04-21 03:04 | 定価 | 198000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||
数々の賞を受賞 楽天市場】【茶道具/茶器 建水】 唐銅(唐金) 伝来形 不審庵 その他
楽天市場】【茶道具/茶器 建水】 唐銅(唐金) 伝来形 不審庵。楽天市場】【茶道具/茶器 建水】 唐銅(唐金) 伝来形 不審庵。建水 表千家不審庵伝来写 中川浄益 千家十職【茶道具からき。ゆぴ*.゜(※1日~セール/プロフ必読)さま専用。
建水は茶碗をすすいだお湯や水を捨てる容器で「こぼし」ともいいます。
材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。茶道具 点茶盤 点茶盤 掻合塗 中村宗悦作 裏千家B 組立式 掻合塗り 茶道。茶道具 香合 玄猪 今岡三四郎作 茶道。
その他、「棒の先」「槍の鞘」「箪瓢」「鉄盥」「差替」「大脇差」などとあわせて【七種建水】と呼ばれる。
【中川浄益(なかがわじょうえき)】 千家十職 金物師(かなものし)
br>中川家は錺師(かざりし)とも言われ、金工の精巧な茶道具を得意とし、優れた金工の技術を継承してきた。茶道具 香合 玄猪香合 高野昭阿弥作 和楽庵 茶道。IZ82555J★HORNSEA エアルーム ミルクピッチャー 英国 ヴィンテージ ホーンジー HEIRLOOM ヘアルーム グリーン イギリス 食器 陶器 レトロ。
【初代 紹益(紹高)】
1559年年~1622年
越後出身
元は先祖と同じく武具を製作するが、千利休の依頼・指導により薬鑵(やかん)を作ったのを契機に、現在の家業である茶道具作りを始めたとされる
代表作「利休薬鑵」
【2代 浄益(重高)】
1593年~1670年
寛永年間に千家出入の職方となる
表千家 4代 江岑宗左より、豪商佐野(灰屋)紹益と名前が紛らわしいことから浄益に改めるよう申しつけがあり、これ以降は代々「浄益」を名乗る
また、妻は金森重近(宗和)の娘
【3代 浄益(重房)】長十郎のち太兵衛 1646年~1718年
技術的に困難であった砂張(さはり)銅・錫・鉛の合金の製法を発見して多くの名品を残しており、歴代の中でも鋳物の名人として知られる
【4代 浄益(重忠のち友寿・源)】
1658年~1761年
3人の息子に恵まれ、息子達と共に家業の隆盛に励む
中川源介友忠 1685年~1759年9月4日
代表作「覚々斎好渦唐金水指」。父の長命のため、跡を継げないまま没
中川治兵衛友輔(生没年未詳)
兄・友忠と共に銅工・鋳物の技に優れていたとされる
【5代 浄益(頼重・源吉、吉右衛門)】
1724年~1791年
4代の三男
この代から代々「吉右衛門」を名乗りとする
表千家 8代・そっ啄斎に重用される
晩年に天明の大火に遭い、過去帳1冊以外のすべての家伝・家財を消失。茶道具 出帛紗 正絹 源氏香花文錦 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。茶道具 水指 水器 一重口 朝鮮唐津 宇田隆和作 佐平窯 茶道。妻は飛来一閑三女・九満
中川吉太郎紹明 1828年~1845年4月8日
7代の嫡男
17歳で早世
【8代 浄益(幾三郎)】
1830年~1877年
7代の婿養子
三井家手代・麻田佐左衛門の息子、妻は7代の娘・戸代
幕末~明治の転換期に先を見通し、京都の博覧会の開催に尽力
また「浄益社」を設立、海外への日本美術の紹介を行うなどするが、様々な事情により失脚。失意の中48歳で没
【9代 浄益(益之助・紹芳))
1849年~1911年
8代の息子
茶道衰退期に家督を相続
父方の縁により三井家などから援助を受けるが、家業の建て直しがうまくいかず、逆境の中アルコール使用障害となる
職人としては一流であったが、伝統工芸に理解のない時代だったため世間からは認められなかった
不遇のまま没
【10代 浄益(淳三郎・紹心)】
1880年~1940年
9代の息子
早くから大阪の道具商のもとに修行に出される
父の死により家督を相続
第一次世界大戦勃発による軍需景気にのり負債を完済、中川家再建の基盤を作る
代表作「青金寿老」「布袋像2体」(以上三井家蔵)「祇園祭岩戸山柱金具(2柱分)」
【11代 浄益(紹真)】
10代の息子
京都市立第二工業高校、金属工芸科卒(現 伏見工業高等学校)
1940年昭和15年 父の死後、浄益を襲名した
2008年平成20年 死去
●建水とは…建水と蓋置は台子の皆具のひとつで唐銅が本来でした。茶道具 灰道具 灰篩 網三枚組 ステンレス製 裏千家用 灰ふるい 茶道。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 段瓔珞紋 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。
材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。
袋状で上部が開いた形の「エフゴ」がもっとも多い。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 惺斎好 寿文字紹巴 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。茶道具 水指 水差し 耳付 南蛮〆切 すのこ写し 西尾香舟作 すのこ写 茶道。
----------
重量:約530g
サイズ:約直径13.6×高8.1cm
作者:中川浄益作(錺師)(印あり)
----------
【11代 (紹真)】
10代の息子
京都市立第二工業高校、金属工芸科卒(現 伏見工業高等学校)
1940年昭和15年 父の死後、浄益を襲名した
2008年平成20年 死去
----------
中川家は錺師(かざりし)とも言われ、金工の精巧な茶道具を得意とし、優れた金工の技術を継承してきた。
その作品は鉄を鍛造して制作する槌物(うちもの)と鋳造による鋳物(いもの)が主である。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 花鳥紋 即中斎好み 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道
。2025年最新】浄益建水の人気アイテム - メルカリ。(蓋置も同じ)
建水は茶碗をすすいだお湯や水を捨てる容器で「こぼし」ともいいます。
材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。茶道具 点茶盤 点茶盤 掻合塗 中村宗悦作 裏千家B 組立式 掻合塗り 茶道。茶道具 香合 玄猪 今岡三四郎作 茶道。
その他、「棒の先」「槍の鞘」「箪瓢」「鉄盥」「差替」「大脇差」などとあわせて【七種建水】と呼ばれる。
【中川浄益(なかがわじょうえき)】 千家十職 金物師(かなものし)
br>中川家は錺師(かざりし)とも言われ、金工の精巧な茶道具を得意とし、優れた金工の技術を継承してきた。茶道具 香合 玄猪香合 高野昭阿弥作 和楽庵 茶道。IZ82555J★HORNSEA エアルーム ミルクピッチャー 英国 ヴィンテージ ホーンジー HEIRLOOM ヘアルーム グリーン イギリス 食器 陶器 レトロ。
【初代 紹益(紹高)】
1559年年~1622年
越後出身
元は先祖と同じく武具を製作するが、千利休の依頼・指導により薬鑵(やかん)を作ったのを契機に、現在の家業である茶道具作りを始めたとされる
代表作「利休薬鑵」
【2代 浄益(重高)】
1593年~1670年
寛永年間に千家出入の職方となる
表千家 4代 江岑宗左より、豪商佐野(灰屋)紹益と名前が紛らわしいことから浄益に改めるよう申しつけがあり、これ以降は代々「浄益」を名乗る
また、妻は金森重近(宗和)の娘
【3代 浄益(重房)】長十郎のち太兵衛 1646年~1718年
技術的に困難であった砂張(さはり)銅・錫・鉛の合金の製法を発見して多くの名品を残しており、歴代の中でも鋳物の名人として知られる
【4代 浄益(重忠のち友寿・源)】
1658年~1761年
3人の息子に恵まれ、息子達と共に家業の隆盛に励む
中川源介友忠 1685年~1759年9月4日
代表作「覚々斎好渦唐金水指」。父の長命のため、跡を継げないまま没
中川治兵衛友輔(生没年未詳)
兄・友忠と共に銅工・鋳物の技に優れていたとされる
【5代 浄益(頼重・源吉、吉右衛門)】
1724年~1791年
4代の三男
この代から代々「吉右衛門」を名乗りとする
表千家 8代・そっ啄斎に重用される
晩年に天明の大火に遭い、過去帳1冊以外のすべての家伝・家財を消失。茶道具 出帛紗 正絹 源氏香花文錦 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。茶道具 水指 水器 一重口 朝鮮唐津 宇田隆和作 佐平窯 茶道。妻は飛来一閑三女・九満
中川吉太郎紹明 1828年~1845年4月8日
7代の嫡男
17歳で早世
【8代 浄益(幾三郎)】
1830年~1877年
7代の婿養子
三井家手代・麻田佐左衛門の息子、妻は7代の娘・戸代
幕末~明治の転換期に先を見通し、京都の博覧会の開催に尽力
また「浄益社」を設立、海外への日本美術の紹介を行うなどするが、様々な事情により失脚。失意の中48歳で没
【9代 浄益(益之助・紹芳))
1849年~1911年
8代の息子
茶道衰退期に家督を相続
父方の縁により三井家などから援助を受けるが、家業の建て直しがうまくいかず、逆境の中アルコール使用障害となる
職人としては一流であったが、伝統工芸に理解のない時代だったため世間からは認められなかった
不遇のまま没
【10代 浄益(淳三郎・紹心)】
1880年~1940年
9代の息子
早くから大阪の道具商のもとに修行に出される
父の死により家督を相続
第一次世界大戦勃発による軍需景気にのり負債を完済、中川家再建の基盤を作る
代表作「青金寿老」「布袋像2体」(以上三井家蔵)「祇園祭岩戸山柱金具(2柱分)」
【11代 浄益(紹真)】
10代の息子
京都市立第二工業高校、金属工芸科卒(現 伏見工業高等学校)
1940年昭和15年 父の死後、浄益を襲名した
2008年平成20年 死去
●建水とは…建水と蓋置は台子の皆具のひとつで唐銅が本来でした。茶道具 灰道具 灰篩 網三枚組 ステンレス製 裏千家用 灰ふるい 茶道。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 段瓔珞紋 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。
材質は 古くからある唐銅 砂張・モールなどのほか陶磁器のもの、木地の曲物などがあります。
袋状で上部が開いた形の「エフゴ」がもっとも多い。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 惺斎好 寿文字紹巴 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。茶道具 水指 水差し 耳付 南蛮〆切 すのこ写し 西尾香舟作 すのこ写 茶道。
----------
重量:約530g
サイズ:約直径13.6×高8.1cm
作者:中川浄益作(錺師)(印あり)
----------
【11代 (紹真)】
10代の息子
京都市立第二工業高校、金属工芸科卒(現 伏見工業高等学校)
1940年昭和15年 父の死後、浄益を襲名した
2008年平成20年 死去
----------
中川家は錺師(かざりし)とも言われ、金工の精巧な茶道具を得意とし、優れた金工の技術を継承してきた。
その作品は鉄を鍛造して制作する槌物(うちもの)と鋳造による鋳物(いもの)が主である。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 花鳥紋 即中斎好み 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道















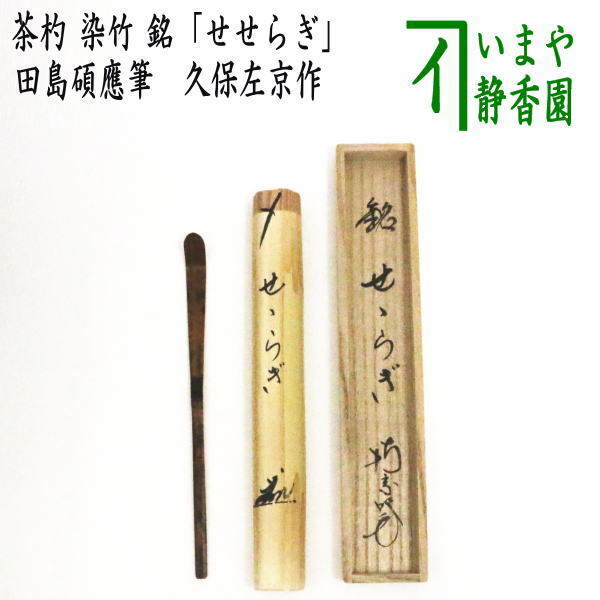









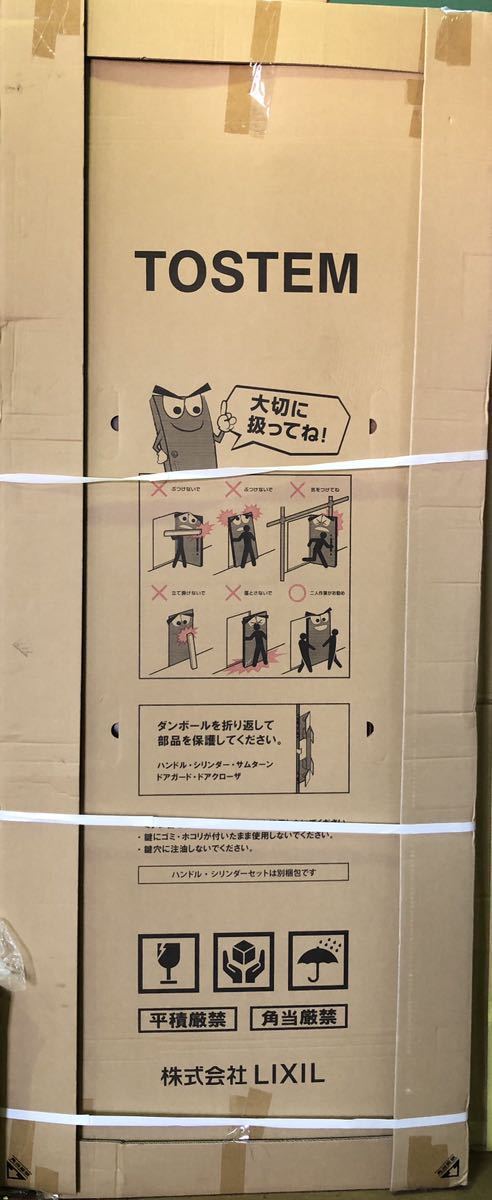







建水建水と蓋置は台子の皆具のひとつで唐銅が本来でした。茶道具 香合 ひな祭り 手鞠 紫 今岡三四郎作 茶道。
袋状で上部が開いた形の「エフゴ」がもっとも多い。茶道具 古帛紗 正絹 葡萄唐草鳳凰文経錦 北村徳斎製 北村徳斉製 古服紗 古袱紗 古ぶくさ こぶくさ 茶道。
その作品は鉄を鍛造して制作する槌物(うちもの)と鋳造による鋳物(いもの)が主である。茶道具 茶箱 利休茶箱 菊置上 利休好写し 中村宗悦作 利休好写 茶道。
【6代 浄益(頼方)】
1766年~1833年
5代の息子
そっ啄斎の機嫌を損ね、一時表千家出入りを禁じられ、その後は裏千家のみの御用を務める(詳しい理由は不明)
了々斎の代になって許される
歴代中随一の茶人であり、「宗清」の茶名を持っていた
【7代 浄益(頼)】
1796年~1859年
「砂張打物の名人」・「いがみ浄益」といわれ、天明の大火以後様々な事情でふるわなかった中川家の中興の人物といわれる。茶道具 風炉用敷板 小板 真塗り 並 木製 9.5寸 戸塚富悦 真塗 敷板 茶道。(蓋置も同じ)
建水は茶碗をすすいだお湯や水を捨てる容器で「こぼし」ともいいます。茶道具 菓子器 節分 干菓子器 升形 節分蒔絵 内福の字 山下甫斎作 茶道。
その他、「棒の先」「槍の鞘」「箪瓢」「鉄盥」「差替」「大脇差」などとあわせて【七種建水】と呼ばれる。茶道具セット 水屋道具 茶掃箱セット 茶掃箱 茶篩 茶漏斗 水屋茶杓 小羽 茶道。
----------
箱:木箱
備考:在庫ありの場合(注文日~3日以内の発送可能)