
新入荷
再入荷
沸騰ブラドン 萩焼き 坂田泥華作 申 猿ぼぼ 萩焼 香合 茶道具 茶道 茶道具 : その他
 タイムセール
タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(※)
999円以上お買上げで代引き手数料無料
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
商品詳細情報
| 管理番号 |
新品 :10648016962
中古 :10648016962-1 |
メーカー | 0b101da120e4a | 発売日 | 2025-05-18 02:40 | 定価 | 38000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||
沸騰ブラドン 萩焼き 坂田泥華作 申 猿ぼぼ 萩焼 香合 茶道具 茶道 茶道具 : その他
茶道具 香合 萩焼 猿ぼぼ 申 坂田泥華作 萩焼き 茶道 : 茶道具。道具 ] - 道具 萩焼 坂田泥華造 銘々皿5客 | ネットショップ圭。十三代 坂田泥華 萩焼煎茶器 | いとう鳳凰堂古美術店。こしひかり12キロ。
飛騨弁では、赤ちゃんのことを「ぼぼ」と言い、「さるぼぼ」は「猿の赤ん坊」の意。
近年では、土産として飛騨地方の観光地で多く見られる。IZ82555J★HORNSEA エアルーム ミルクピッチャー 英国 ヴィンテージ ホーンジー HEIRLOOM ヘアルーム グリーン イギリス 食器 陶器 レトロ。茶道具 茶箱 利休茶箱 菊置上 利休好写し 中村宗悦作 利休好写 茶道。それが猿の赤ちゃんのように見えたことから猿の赤ちゃん(猿ぼぼ)といわれ、猿は「去る」と書き「災いが去る(猿)」「疫病が去る(猿)」ことからも、安全を祈願した。
また、農作業をしている時に、そばで寝ていた赤ちゃんが田んぼの溝に落ちそうになったところ、猿が助けた。茶道具 水指 水器 一重口 朝鮮唐津 宇田隆和作 佐平窯 茶道。茶道具 風炉用敷板 小板 真塗り 並 木製 9.5寸 戸塚富悦 真塗 敷板 茶道。
坂田家は萩焼の 始祖である李勺光(りしゃくこう)の流れをくむ家柄で、深川萩四家の一つ
(深川萩四家 とは現在、坂田泥華窯の他、坂倉新兵衛窯、田原陶兵衛窯、新庄助右衛門窯の四窯元 がある)
【初代 李勺光】
【2代 山村新兵衛光政 生年不詳~1658年明暦4年】
【3代 山村平四郎光俊 生年不詳~1709年宝永6年】
【4代 山村弥兵衛光信 生年不詳~1724年享保9年】
【5代 山村源次郎光長 生年不詳~1760年宝暦10年】
【6代 坂倉藤左衛門 生年不詳~1770年明和7年】
【7代 坂倉五郎左衛門 生年不詳~1792年寛政4年】
【8代 坂田善兵衛 生年不詳~1805年文化2年】
【9代 坂田甚吉 生年不詳~1818年文化15年】
【10代 坂田要四郎 生年不詳~1886年明治19年】
【11代 坂田鈍作 生年不詳~1916年大正5年】
【12代 坂田泥華(本名:浩三) 生年不詳~1934年昭和9年】
【13代 坂田泥華(14代 泥珠 同一人物)(本名:一平)】
(泥華井戸には、おおらかで特有の轆轤造形がある。他には焼成時に釉薬を剥ぎ取る事により御本風の柔らかい斑文を表現した剥離釉等、新技法にも取り組んだ。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 段瓔珞紋 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。茶道具 菓子器 節分 干菓子器 升形 節分蒔絵 内福の字 山下甫斎作 茶道。父・12代泥華に師事作陶。伝統の家法を習得
1950年昭和25年 13代 坂田泥華を襲名
1962年昭和37年 頃より加藤土師萌の指導を受ける
1964年昭和39年 日本工芸会正会員となる
1965年昭和40年 山口県芸術文化振興奨励賞を受賞
1968年昭和43年 山口県美術展審査員を委嘱
1970年昭和45年 中国文化賞を受賞
1972年昭和47年 山口県指定無形文化財に認定
名古屋オリエンタル中村個展の出品作品が宮内庁に買い上げ
1974年昭和49年 迎賓館に水指を納入。茶道具 水指 水差し 耳付 南蛮〆切 すのこ写し 西尾香舟作 すのこ写 茶道
。萩焼【坂田泥華】湯呑 澄む。
飛騨弁では、赤ちゃんのことを「ぼぼ」と言い、「さるぼぼ」は「猿の赤ん坊」の意。
近年では、土産として飛騨地方の観光地で多く見られる。IZ82555J★HORNSEA エアルーム ミルクピッチャー 英国 ヴィンテージ ホーンジー HEIRLOOM ヘアルーム グリーン イギリス 食器 陶器 レトロ。茶道具 茶箱 利休茶箱 菊置上 利休好写し 中村宗悦作 利休好写 茶道。それが猿の赤ちゃんのように見えたことから猿の赤ちゃん(猿ぼぼ)といわれ、猿は「去る」と書き「災いが去る(猿)」「疫病が去る(猿)」ことからも、安全を祈願した。
また、農作業をしている時に、そばで寝ていた赤ちゃんが田んぼの溝に落ちそうになったところ、猿が助けた。茶道具 水指 水器 一重口 朝鮮唐津 宇田隆和作 佐平窯 茶道。茶道具 風炉用敷板 小板 真塗り 並 木製 9.5寸 戸塚富悦 真塗 敷板 茶道。
坂田家は萩焼の 始祖である李勺光(りしゃくこう)の流れをくむ家柄で、深川萩四家の一つ
(深川萩四家 とは現在、坂田泥華窯の他、坂倉新兵衛窯、田原陶兵衛窯、新庄助右衛門窯の四窯元 がある)
【初代 李勺光】
【2代 山村新兵衛光政 生年不詳~1658年明暦4年】
【3代 山村平四郎光俊 生年不詳~1709年宝永6年】
【4代 山村弥兵衛光信 生年不詳~1724年享保9年】
【5代 山村源次郎光長 生年不詳~1760年宝暦10年】
【6代 坂倉藤左衛門 生年不詳~1770年明和7年】
【7代 坂倉五郎左衛門 生年不詳~1792年寛政4年】
【8代 坂田善兵衛 生年不詳~1805年文化2年】
【9代 坂田甚吉 生年不詳~1818年文化15年】
【10代 坂田要四郎 生年不詳~1886年明治19年】
【11代 坂田鈍作 生年不詳~1916年大正5年】
【12代 坂田泥華(本名:浩三) 生年不詳~1934年昭和9年】
【13代 坂田泥華(14代 泥珠 同一人物)(本名:一平)】
(泥華井戸には、おおらかで特有の轆轤造形がある。他には焼成時に釉薬を剥ぎ取る事により御本風の柔らかい斑文を表現した剥離釉等、新技法にも取り組んだ。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 段瓔珞紋 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。茶道具 菓子器 節分 干菓子器 升形 節分蒔絵 内福の字 山下甫斎作 茶道。父・12代泥華に師事作陶。伝統の家法を習得
1950年昭和25年 13代 坂田泥華を襲名
1962年昭和37年 頃より加藤土師萌の指導を受ける
1964年昭和39年 日本工芸会正会員となる
1965年昭和40年 山口県芸術文化振興奨励賞を受賞
1968年昭和43年 山口県美術展審査員を委嘱
1970年昭和45年 中国文化賞を受賞
1972年昭和47年 山口県指定無形文化財に認定
名古屋オリエンタル中村個展の出品作品が宮内庁に買い上げ
1974年昭和49年 迎賓館に水指を納入。茶道具 水指 水差し 耳付 南蛮〆切 すのこ写し 西尾香舟作 すのこ写 茶道














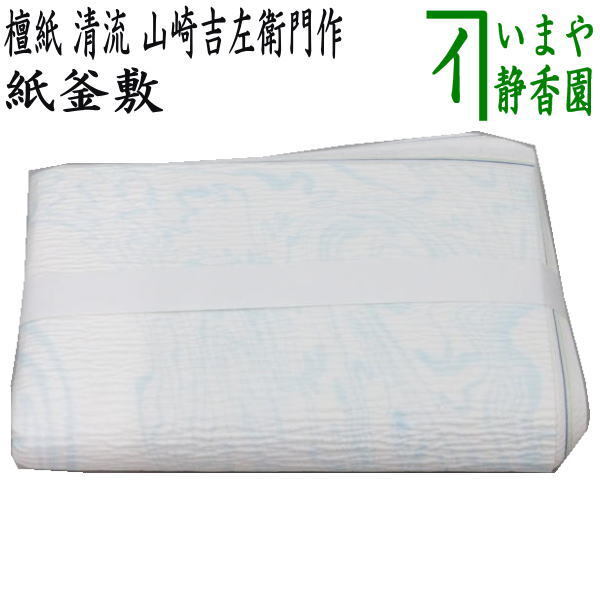
















猿ぼぼ飛騨高山など岐阜県飛騨地方で昔から作られる人形。茶道具 香合 玄猪香合 高野昭阿弥作 和楽庵 茶道。
いろいろな説がありますが、
赤い布で作られた人形で、天然痘(てんねんとう)などが万延した時代に、病気災いから守ってくれるお守りとして作られた。茶道具 出帛紗 正絹 源氏香花文錦 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。
その感謝の意味を込めて家族が猿ぼぼ人形を作って持つようになったとい説もあります。茶道具 灰道具 灰篩 網三枚組 ステンレス製 裏千家用 灰ふるい 茶道。)
1915年大正04年 12代 泥華(本名:浩三)の長男で山口県生
1933年昭和08年 山口県立萩商業学校を卒業。茶道具 出帛紗 正絹 紹巴織り 惺斎好 寿文字紹巴 出服紗 出袱紗 出ぶくさ だしぶくさ 茶道。山口県選奨(芸術文化功労)を受賞
1975年昭和50年 東京三越個展の出品作品が宮内庁に買い上げ
1976年昭和51年 日本工芸会理事に就任
1981年昭和56年 紫綬褒章を受章
1987年昭和62年 勲四等旭日小綬章を受章
2004年平成16年 長男・慶造が早世したために15代坂田泥華を追贈し、自らは14代天耳庵:坂田泥珠と号す
2010年平成22年2月24日肺炎で死去、94歳没